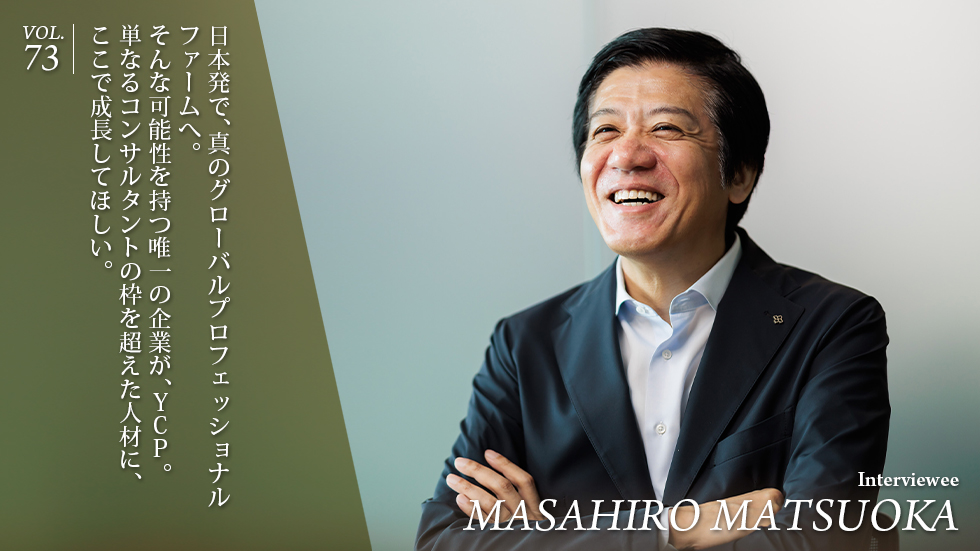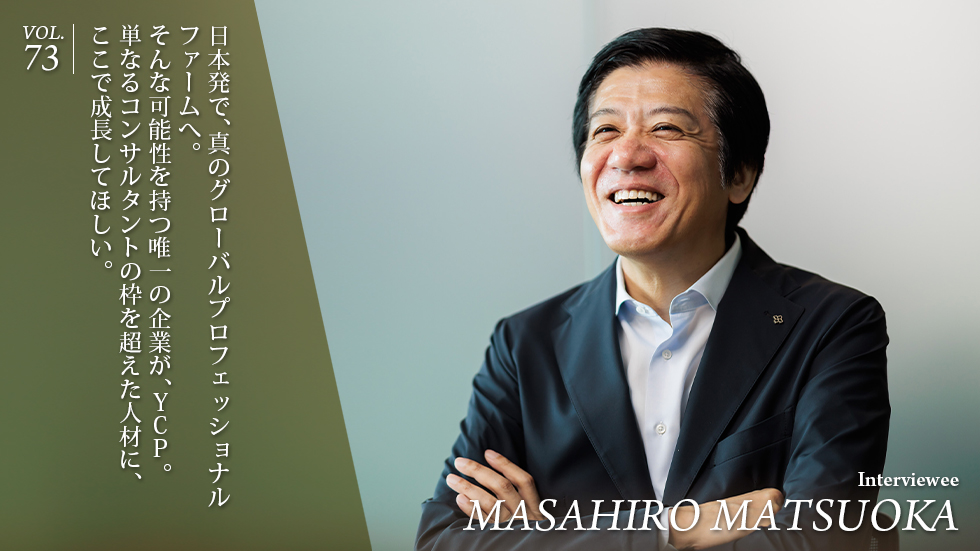Vol.73
日本発で、真のグローバルプロフェッショナルファームへ。そんな可能性を持つ唯一の企業が、YCP。単なるコンサルタントの枠を超えた人材に、ここで成長してほしい。
YCP Japan
グループオフィサー マネージングパートナー 日本地域統括責任者松岡真宏氏
公開日:2025.10.6
インタビュアー
太田
アジアを中心にグローバルに事業を展開し、幅広い分野におけるアドバイザリーサービスを通してグローバル企業や現地企業の経営を支援しているYCP。通常のコンサルティングファームとは一線を画する存在であり、業界内での評価も高い。このYCPに2025年1月から参画し、日本地域統括責任者を務めているのが松岡真宏氏だ。過去に産業再生機構で実績を上げ、自らコンサルティングファームを創業した経歴をもつ松岡氏は、なぜYCPに参加したのか。同社が秘める可能性と今後の事業戦略、これから求められる人材について話をうかがった。
産業再生機構で企業再生案件に携わり、“インサイダー”として経営を変える面白さに魅せられた。
- 太田
- まず初めに、松岡さんのご経歴をお伺いできますでしょうか。
- 松岡
- 私は社会に出てから35年ほど経ちますが、前半と後半で企業に対してのスタンスが異なる人生を送っています。前半は証券アナリストという立場から、外部からの目で経営を分析して投資家に情報を伝える“アウトサイダー”として企業と向き合ってきました。
一方、後半は逆に企業の中に入り込んで“インサイダー”として企業の経営を変革していくポジションで奮闘。いわば前半は「外圧」、後半は「内圧」で企業を変えていく仕事に携わってきた感じでしょうか。
- 太田
- 松岡さんが新卒時に“アウトサイダー”の立場から企業経営に関わっていくことを選択されたのは、どのようなお考えからですか。
- 松岡
- 私は大学で経済学を専攻しましたが、マクロ経済学にあまり関心が持てず、むしろ企業や消費者の行動から経済を捉えるミクロ経済学のほうに惹かれたんですね。それを究めるためには、企業分析を専門とする仕事に就き、その技術を磨くのが一番の近道だと考え、希望するポジションがあった野村総合研究所に入社。その後、UBS証券に移って引き続き証券アナリストを務めましたが、一貫して小売・消費セクターを専門にキャリアを重ねました。
- 太田
- その後、松岡さんは産業再生機構に参画され、キャリアの大きな転機を迎えられています。これはどのような経緯だったのしょうか。
- 松岡
- 産業再生機構が発足した2000年代前半は、日経平均が1万円を切る状況がずっと続いていて、日本経済全体がメルトダウンするのではないかという危機感に襲われていたんですね。そんな中で当時の小泉政権が、大手企業が抱える不良債権を処理して再生させることに特化した特殊会社を設けることを掲げ、それが産業再生機構でした。たまたまこちらの機構に知り合いがいて、お声がけいただいたのがきっかけですが、個人的にも当時、いまこの問題に取り組まなければ、きっと人生で後悔するという思いがありました。
当時、ダイエーをはじめ、かつて隆盛を極めた日本の小売業が莫大な不良債権に喘いでおり、小売セクターに貢献してきた私が力にならなければ誰がやると、そんな勝手な使命感を抱いて参画しました(笑)。
- 太田
- それを契機に“アウトサイダー”から“インサイダー”に転換されたというわけですね。
- 松岡
- 実は当初、これほど長く企業再生のコンサルティングやM&A アドバイザリーに携わるとは想定していなくて、数年間、産業再生機構での役目を果たせば、また投資銀行の世界に戻ろうと思っていたんです。でも、実際に携わってみるとこれが本当に面白くて“インサイダー”から抜け出せなくなってしまった。
もうお亡くなりになられましたが、産業再生委員長を務められていた高木新二郎先生が「35歳から45歳の仕事で、老後までの自分の人生が決まる」とおっしゃられていたのをすごく覚えていて、事実、いま企業再生の世界で飯を食わせていただいているのも、やはり産業再生機構での濃密な経験があったからこそだと思っています。
- 太田
- 企業再生のコンサルティングが想像以上に面白かったとのことですが、具体的にどこに魅力をお感じになられたのでしょうか。
- 松岡
- 外部から企業を分析するのは、いくら研ぎ澄ましてもやはり“アウトサイダー”として理解するしかなく、半分自分の思い込みの世界なんですね。しかし“インサイダー“として中に入ると、企業がのたうち回るリアルな経営が見えてきて、それがとても面白かった。
しかも、投資銀行では経営学や経済学という狭いアプローチで企業の分析をしていくわけですが、企業の中に入ると、人と人が繋がって組織や事業が機能していくという社会学的な要素や、法律や制度に経営が縛られる部分もあるという法学的な要素も絡んできて、自分には無縁だった領域とも関わっていかなければならない。
ひとつの種目を究めて勝利するだけでは栄光を勝ち取れず、いわば十種競技で優勝することが求められるような世界で、そこに私は非常に惹かれました。当時、それを果たせる企業が存在しなかったので、ならば自分たちで作ろうとフロンティア・マネジメントを立ち上げたのです。
- 太田
- 松岡さんが共同創業者であるフロンティア・マネジメントは、一般的には経営コンサルティング会社として認識されています。経営コンサルティングは外部からアドバイスを行う“アウトサイダー”のようにも見受けられますが、ご自身が手がけられてきた企業再生コンサルティングというのは、通常の経営コンサルティングとは異なるものなのでしょうか。
- 松岡
- 企業再生というのは、実に多様な知識を混ぜ合わせて取り組まなければならないテーマです。さらなる成長のためのビジネスモデルを構築すればいいというものではなく、M&Aなども絡んできて、法務や税務などビジネス戦略以外の課題解決が大きなウエイトを占めており、一般的なコンサルティングよりも知見を発揮しなければならない領域が広いかと思います。


コンサルタントは武器商人であってはならない。あるべき理想を体現していたのがYCPだった。
- 太田
- 2025年初頭に松岡さんはフロンティア・マネジメントからYCPに移籍されたわけですが、どのような経緯で参画されたのでしょうか。
- 松岡
- 個人的には私は、日本経済というのは大企業が変革されない限り、大きな変化は起きないと思っています。そして日本経済がより成長していくためには、やはり海外の需要とか人材とか技術を取り込んでいく必要があり、大企業がそうした資産を持つ会社ともっと積極的に経営統合したりアライアンスを組むべきだというのが私の思想。以前在籍していたフロンティア・マネジメントの方向性が少し異なってきたこともあり、やりたいことを実現できる環境を求めてYCPに参画した次第です。
- 太田
- YCPのどのような点に可能性をお感じになられたのですか。
- 松岡
- YCPは日本で生まれた企業ですが、まだ社員数が100名にも満たない段階でグローバル化を掲げて本社を香港に移し、さらに現在はシンガポールに移すなど、非常に先見性があるマネジメントをしています。さらに、自社よりも図体の大きな海外のアドバイザリー企業を、インドや中国、東南アジアで買収し、一気にグローバル化を果たしました。
我々がコンサルタントとして企業を変革していくのであれば、我々自身も変革していかなければならない。口先だけのコンサルタントは、言葉は悪いですが武器商人のようで、武器を売ってあとは勝手に戦ってくれ、というコンサルタントが残念ながら多いのが実情。企業にグローバル化を促すのなら、自らもグローバル化することが必要であり、それを真に実践しているのはYCP以外見当たりませんでした。
- 太田
- コンサルタントは武器商人であってはならない、というのは確かにおっしゃる通りです。松岡さんご自身は、コンサルタントの醍醐味はどこにあるとお考えですか。
- 松岡
- そもそも私は自分自身がコンサルタントだとはあまり思っていません。過去、フロンティア・マネジメントを立ち上げた時も、コンサルティング会社を作ったのではなく、企業の経営を支援する機能を持つ会社を作ったという意識です。
かつてコンサルタントというのは、企業経営における戦略家や参謀のような捉え方をされていましたが、それではもう時代遅れだと思っています。企業のCEOをはじめCXOのすぐ横にいて、彼ら彼女らが考えるすべての論点に対して、一緒に議論して解決する力となることが大切。それができることに我々の価値があり、私が醍醐味を覚えるのもその点です。
- 太田
- いま松岡さんがお話しされた、CXOのすぐ隣のポジションを務めるのは非常に難しいことだと思います。それを担うために必要とされるのは、どんな素養や経験なのでしょうか。
- 松岡
- やはり事業会社での経験だと思います。経験していないことをいくら懸命に説いても、上滑りして響かない。ですから、YCPでは顧客企業のマネジメント層に積極的に人材を送り込み、経営に携わる機会を提供しています。経営の当事者となるのは本当に大変で、私も過去、産業再生機構でダイエーやカネボウの役員を務めた時、いま振り返ってもあれ以上苦しい経験はありませんでした。
でもその苦悩を身をもって味わったからこそ、いまの私がある。真に経営を支援できる人材になるためには、そうした苦しいポジションも進んで受け入れる胆力も重要だと思いますね。
- 太田
- では、あらためてYCPがどのような事業を推進し、どのような特徴をお持ちなのかをご紹介いただけますか。
- 松岡
- 現在、YCPで最も大きな事業部門はMSD(Management Services Division)と呼ばれる組織ですが、この名称にコンサルティングという言葉は入っていないんです。経営に対してサービスを提供することがこの部門のミッションであり、顧客の成長のためには新羅万象を扱っていく。
これは、創業者の石田(裕樹氏/グループCEO)の思想であり、私自身の思想とも綺麗にシンクロしていて、だからこそYCPに参画したわけですが、ここが普通のコンサルティング会社とは決定的に異なる点だと思います。美しい戦略の絵を描いて、特定のメソッドを適用していくような関わり方は一つもなく、顧客が抱える問題と論点を徹底的に浮き彫りにし、多角的に分析を行って個別に処方箋を編み出していく。
すべてがテーラーメイドであり、汎用性のあるパッケージを提供していくような仕事ではない。ですから顧客常駐型の案件が増えており、私も若いメンバーに対して単に常駐するだけではなく、顧客企業に入り込み、信用を得て役員やラインマネージャーを務めるように発破をかけています。そうすると顧客の経営に対してより真剣味が増し、大変な思いを味わう一方で、能力は格段に向上していく。そんな経験を広く積ませたいというのが私のマネジメント方針です。
- 太田
- グローバルであることもYCPの大きな特徴だと思いますが、この点についてもご説明いただけますか。
- 松岡
- 現在、香港、シンガポール、上海などアジアを中心に20以上の国と地域に拠点を構え、若手からシニアまで日本で採用した人材を派遣しています。また、現地に赴任しなくても、いまや案件の3割から4割は海外のメンバーと連携しながら実行しており、グローバルな環境で自分を高めることができる。近い将来、我々が手がける事業の大半がクロスボーダーになってもおかしくないと思っており、海外を相手にキャリアを積みたい方にとっても、YCPはチャンスにあふれた魅力的な場です。


これからの2年間で、YCPをもう一つ作り上げる。我々が掲げるビジョンを共有できる人材を求めたい。
- 太田
- いまご紹介いただいた特徴も踏まえて、今後のYCPの事業戦略について教えていただけますか。
- 松岡
- 組織軸、地域軸、サービス軸の3つからお話しします。まず組織軸では、いま日本のオフィスでは100名ほどの人材を擁していますが、これを2~3年以内に300名体制にまで拡大する方針です。ちなみに、グループCEOの石田も、グローバル全体の社員数を現在の500名から、早急に1000人体制、あるいは2000人体制にすることを目標としています。日本でも海外でも、現在の陣容をもう一つ二つ新たに作るようなイメージで、大胆に成長を果たしていく考えです。
地域軸では、現在は東アジアからインドまでをカバーしていますが、中東やアフリカ、さらにヨーロッパまで我々のエリアを拡げていきたい。
そしてサービス軸に関しては、ソリューションをもっと深堀りしていく戦略を進めていきます。すでに日本では、マネジメントサービスだけではなくDXやサステナビリティなど、よりセグメントを絞ったソリューションを作って展開しています。海外においても、たとえば東南アジアの物流に強い会社を買収して提供できるサービスの領域を広げるなど、ソリューションに深みを作っていくことにも注力していきます。
- 太田
- ものすごいスピードでの成長をお考えになられているわけですね。
- 松岡
- 確かに、これから2年ほどで同じ規模の組織をもう一つ新たに作ろうとしているわけで、かなりのスピード感に映るかもしれません。しかし、世界はもっと早く動いている。
特にコンサルティング業界は、自社の経営を棚に上げている企業が多いと思います。コンサルタントは決して特権階級ではない。上場すると株主の意向に左右されて使命がぶれると宣うコンサルティング会社もあるようですが、それは上場するからではなく、自社株を持つ社長や役員が自分のポジションや持株比率など私利私欲にこだわってしまうから、ぶれるのです。
日本はコンサルティング会社が上場できる環境にあるのですから、上場してもっと強くなるべき。いろんなステークホルダーと堂々と渡り合い、変化にスピーディーに対応しながら事業を大きく拡げ、実現したい世界を力強く目指すべきだと思いますね。
- 太田
- 今後、顧客の経営を支援するためにクロスボーダーのM&Aアドバイザリーにも力を入れて取り組まれるかと思いますが、他の戦略ファームと異なるYCPならではの価値提供をどのようにお考えですか。
- 松岡
- M&Aだけにフォーカスするのではなく、実行した後にどのようにお客様全体の事業を改善していくのか、ときには買収先の経営陣にまで入り込み、確実に価値を生み出すところまで深く関わっていくのがYCPの流儀です。
M&Aアドバイザリーだけ、戦略コンサルティングだけというのは歪むと思っていて、どちらかしか手がけていないと、自社の利益のためにお客様に不利益をもたらすような提案をしかねない。ですから、その時々の課題に対してM&Aすべきなのか、それとも経営改革すべきなのか、両面から最適な解を示せることが我々のあるべき姿だと思っています。
- 太田
- これから組織をさらに拡大されていくとのお話しですが、採用にあたってどのような人材を求めていらっしゃいますか。
- 松岡
- IQが高いだけの人材は、これからのYCPにはおそらくフィットしないと思います。我々が提供するサービスは、いわば「混合治療」のようになっており、自分にはない専門性を持った人たちと、互いにリスペクトしあってこの混合治療のための処方性が書けるかが大切になる。そこには、専門外のことを聞き出す力や柔軟に発想する力も求められます。
そして、世界の変化に敏感な人がいい。過去を振り返ると、1980年代までの冷戦時代は、先進国と呼ばれる西側の国家はごく限られていて、日本もその一国として温い環境下で経済を発展させることができた。当時の大企業はその恩恵を受けて、コンサルタントなどを使わずとも成長できた。すべて自前で経営できたのは、決して能力があったわけではなく、たまたま環境が良くて楽な状況だったからに過ぎない。しかし、ベルリンの壁が崩壊してグローバル化が一気に進み、中国やインドなどの新興国が急速に台頭し、インターネットによる情報網も発達して激動の社会が到来しました。
こうした状況では、すべて自前で賄えるはずもなく、外部の専門人材の使わない経営者は無能の烙印を押されても仕方がない。逆に我々にとってはエキサイティングな状況になっており、常に変化がもたらす新しい価値を学び続けて、いろんな世界のいろんな人と交流し、そこから得たものを自分に投影できるような人に参加していただきたいです。特に事業会社で経営企画や事業企画に携わっていた方で、新たなオポチュニティを求めているような方は大いに歓迎します。
- 太田
- では最後に、YCPでのキャリアに興味をお持ちの読者の方々にメッセージをお願いします。
- 松岡
- 日本発で世界に名を轟かせるグローバルプロフェッショナルファームになれる、そんな可能性を秘めた唯一の企業がYCPだと私は思っています。これから参加いただくみなさんとともに、ぜひそれを成し遂げていきたいので、意欲溢れる方に当社の門を叩いていただきたいですね。
※インタビュー内容、企業情報等はすべて取材当時のものです。